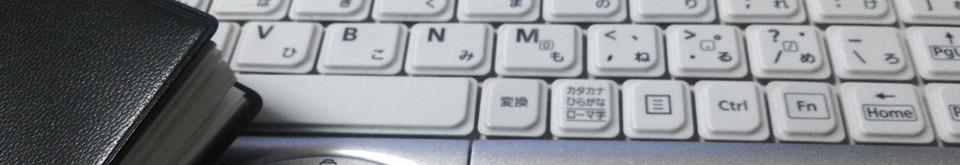サーチマン佐藤です。
こんにちは。
今日は、リーダーシップのお話です。
チームで仕事する時、一般的には
メンバーとコミュニケーションが大事と言われますが、
これを「民主主義」とはき違えて、
多数決で決めればOK、
みたいな勘違いすると、
(皮肉なもので)
プロジェクトは逆に迷走する。
そりゃ、平和な時は、多数決OKですよ。
例えば、
「今日、飯どこ行く?」
「多数決で決めようぜ」
とか。
でも、アナタの仕事は、我々のプロジェクトは、
いつも緊急事態の戦争と同じですよね。
そんな状態(仕事)では、
何をおいても、
一番大事なことは、
(リーダーたる)
「アナタの命令に従わせる事」
これが全てです。
じゃあ、その権威づけはどうするのか?
一般的には、(リーダーとして誰もが納得できる)
「常識的で、合理的で、正しい命令」を出していれば、
部下は(感心し尊敬し)自然と従うようになる。
とか言われていますが、
本当でしょうか?
私は懐疑的ですけどね。
そもそも、そんな立派な命令をいつも出せないし、
リーダーだって「神」じゃないんだから、間違うこともある。
いや、むしろ(誤解を恐れずに言えば)
合理的じゃない非常識な命令にこそ、
リーダーの権威は生まれる。
逆説的ですが、「神」にもなれる。
そう思いますけどね。
「えっ??」ですか(笑)
いーえ、アナタの
聞き間違いじゃないですよ。
もう一度言いますが、
「合理的じゃない非常識な命令」にこそ、
むしろ、リーダーの権威は生まれる。
「????」ですよね(笑)
無理もありません。
我々は、民主主義にどっぷり浸かってますから。
でも、本当ですよ。
かつて「神」なみのリーダーシップを発揮した人は、
この方法をよく使っています。
ちょっと振り返ってみましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【権威づけ】ここぞという時の非常識さ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
先日、NHKの
「大リーグを超えろ、V9巨人・川上哲治監督」
という番組を観ました。
もちろん川上監督は、プロ野球の世界で、
前人未到の9連覇を成し遂げた名監督。
2013年に亡くなりましたが、
今回の番組では、生前の日記が
新たに川上家から提供され、
監督の(偉大な)
「リーダーシップ論」が語られました。
その中で、
こんなエピソードがあるんですね。
1961年、南海との日本シリーズ。
巨人が2勝1敗とリードした第4戦が雨天中止に。
土砂降りの雨。
普通は休みか、室内で練習ですよね。
しかし、川上哲治監督は、
荒天の中、多摩川グラウンドで練習を命じました。
「風邪ひいたらどうする?」
「こんな練習は全く意味がない」
コーチも選手も(特に、広岡選手、森選手は)、
大反対だった。
しかし、それでも監督は、
ボールをたき火で乾かせながら、
雨中の練習を決行させ、
(あの長嶋、王選手も含めて)
選手たちはずぶ濡れになりながら、バットを振った。
何故か?
いみじくも、王さんが語っています。
練習そのものには意味がない。
監督の命令は絶対。
「チームは監督の命令で動く」と、
メディアにも選手にも理解させた瞬間だったと。
そう。
「合理的じゃない非常識な命令」が、
リーダーの権威を生んだ瞬間でもあるのです。
例えば、小泉首相。
彼の政策は評価できないものがありますが、
稀有なリーダーシップを発揮した総理大臣ではある。
そんな小泉首相は、
郵政民営化法案が参議院で否決された時、
「衆議院」を解散し、総選挙に踏切りました。
ちなみに、衆議院は法案が通過しているわけで、
論理的には、全くおかしいですよね。
でも、小泉首相は、
「信念だ。殺されてもいい」と断行しました。
※(小泉首相)リーダーシップの黄金パターン
この気迫。
「合理的じゃない非常識な命令」が、
リーダーの権威を生むのです。
そして、アップル創業者の
スティーブ・ジョブス氏。
iPod開発の初期のころの話です。
開発を命じられたエンジニアたちが、
ジョブズ氏に試作品をもっていきますが、
ジョブズ氏は、それを見て不満をもち、
「もっと小さくしろ」と一喝。
しかし、エンジニアたちは、技術的に、
これ以上小さくすることは不可能だと説明しました。
ジョブズ氏は激怒し、
水槽の中に、そのiPodを放り込むのです。
ブクブクと沈むiPod。
「あっ、何てことするんですか?」
とキレそうになるエンジニアたち。
ここで、ジョブス氏は、
「ブクブクと気泡がでるなら、もっと小さくできる」と、
再開発を命じました。
いくら小さくても気泡くらいでるでしょ?(苦笑)
いや、もしかしたら、
合理的な説明なのかもですが、
少なくとも、
水槽にiPodを放り込む非常識さが、
彼の「命令は絶対」だと権威づけた瞬間です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【復習】我々がリーダーになった時・・・・
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いかがでしたでしょうか?
偉大なリーダーの権威づけのエピソード。
殺意さえ感じる信念。
でもね、勘違いして欲しくないので、
復習しておきましょうか。
リーダーは、基本的には、
「常識的で、合理的で、正しい命令」を出さなければいけません。
ここが前提ですよ。
これを間違えないでくださいね。
だからこそ、他人より経験があり、
優れた人がリーダーになるわけですから。
でもね、こと権威づけに関しては、
合理的とか常識的とか、全く関係ないのです。
「命令に従わせる事」が全てであり、
合理的とか常識的とか、
その上に、
アナタの命令があるのです。
順番を間違ってはいけません。
だからこそ、その権威づけは、
「合理的じゃない非常識な命令」こそが、
試金石にもなる。
ここでアナタが信念を持ち、
つっぱり切れるかどうか?にかかっているのです。
えっ?!
それは、
川上監督、小泉首相、スティーブ・ジョブス、
偉大な人だから、出来たって?
う~ん。
確かに、そうかもですね。
我々のように、普通で弱気のSEにとっては、
権威づけは、そりゃ大変ですよ。
私も、命令を聞かない部下を呼び出して説得したり、
会議で(がんばって)怒鳴ったり、
そりゃ、大変でした(苦笑)。
でもね、そんな私でも、
試行錯誤すれば、なんとか方法論は身についたりもする。
アナタも出来ると思いますし、
特にね、私が提供した
「弱気SEがダントツマネージャー」をお取り寄せした方は、
P13 「試金石を投げろ」
P18「教育の法則」
ここを熟読、復習してみてください。
そして、この方法を真似てみてください。
ふつーの人でもリーダーシップを発揮できる
具体的方法が書いてありますので。
ちなみに、先日購入頂いた方から、
こんな感想もありました。
———————————–
昨日購入し、一気に読んでしまいました。
勇気を出して購入した甲斐がありました。
本に書いてあること、セミナーの講師が行っていることが、
きれいごと過ぎて、まったく効果が感じられない、
というあたりは非常に共感をもてました。笑
本書のなかで、
関係者をコントロールする方法、
●●の使い方、などなど目からうろこでした。
これらの点は、いつも困っていたので、
積極的に活用していきたいと思います。
———————————–
(●●伏字は、ご了承ください)
そう。
私も、最初は具体的な方法がわからなかったし、
いつも困っていました。
だって、
我々は民主主義をはき違えていたから。
でも、今はわかる。
その呪縛は解けたのです。
リーダーのマインドセットとして、
「正しい命令を出す」のは、
確かに大事なのですが、
でも、それよりも何よりも、
まずは、「アナタの命令が絶対」ということ。
そして、その権威づけは、
むしろ、合理的じゃない非常識な命令にこそ、
生まれる可能性がある。
参考にしてみてくださいね。
ではでは。
またお会いしましょう。
ありがとうございました。
●追伸
この続きは、「リーダーが、注意したり叱ったりする時に重要なこと。」
———————————————–
このブログだけで言えない話はメルマガで。
メルマガ購読は、こちらから
(登録後、解除する場合は、メルマガ内の解除クリックから簡単に解除できます)
※登録後、確認メールが届きます。
※このブログ以外の面白い話満載です。
———————————————–
このブログの簡単な感想・ご意見はこちらから
[contact-form-7 404 "Not Found"]
———————————————–